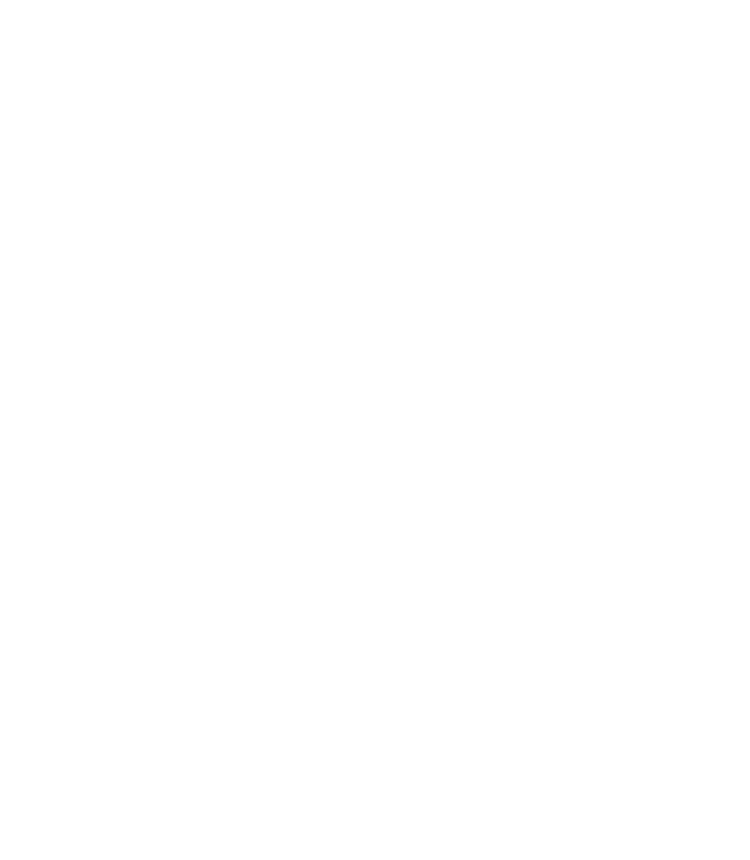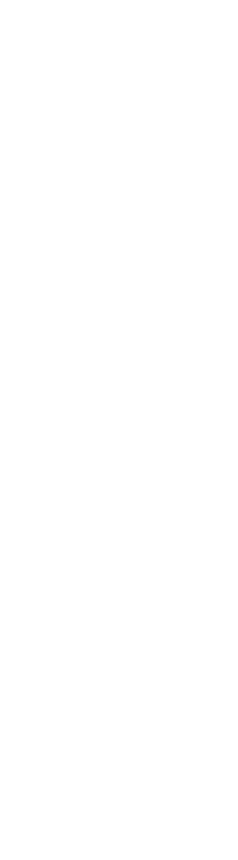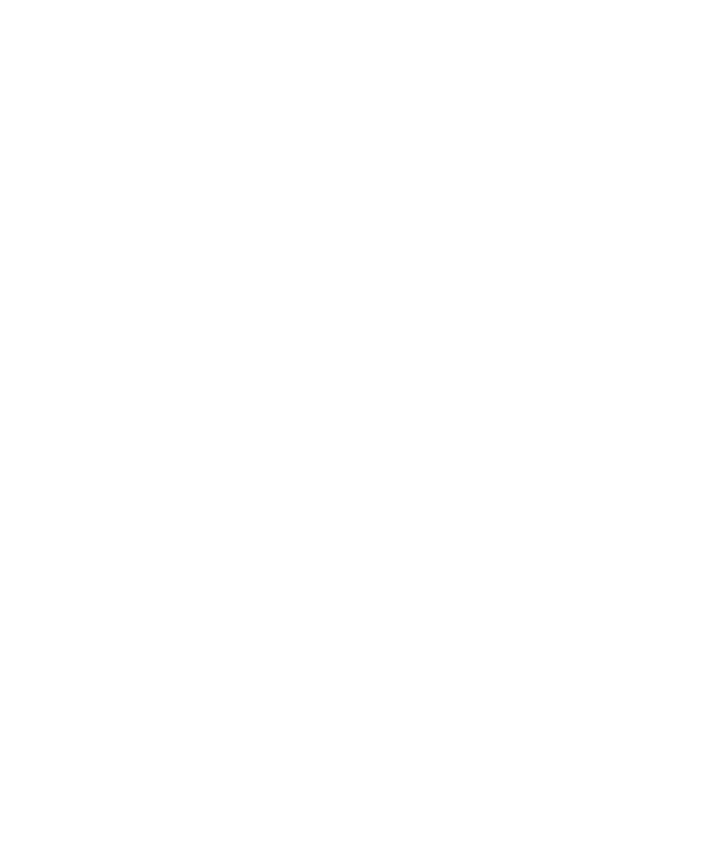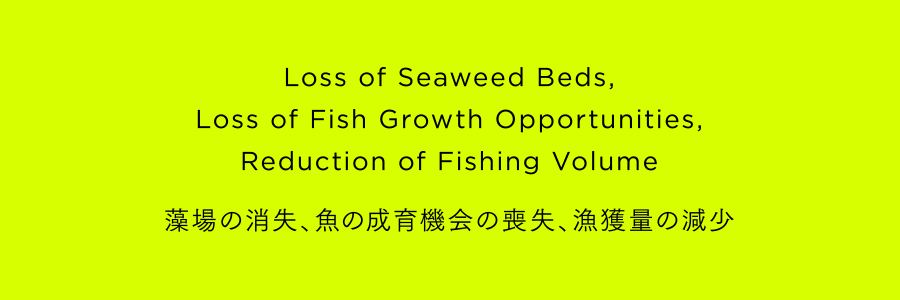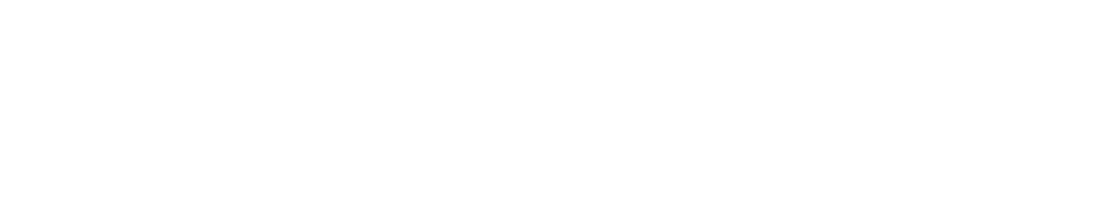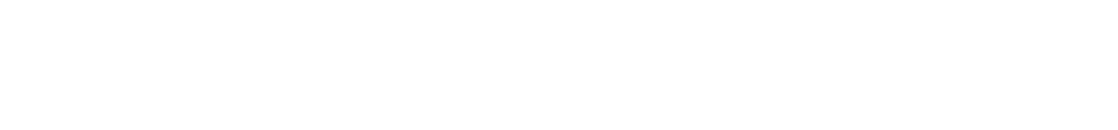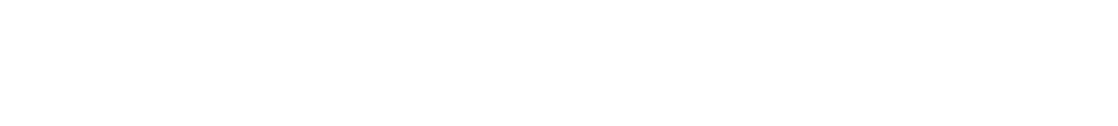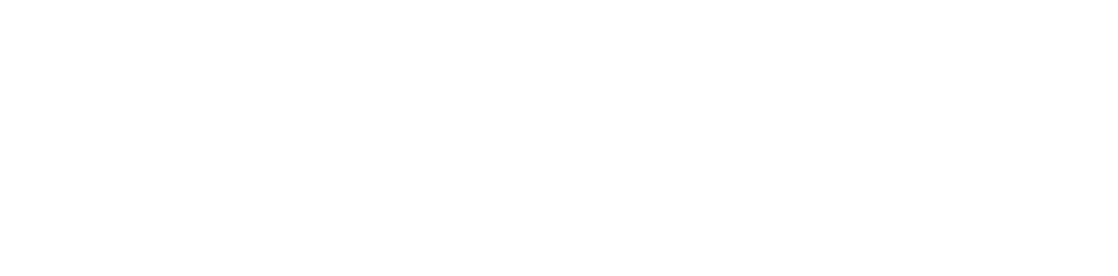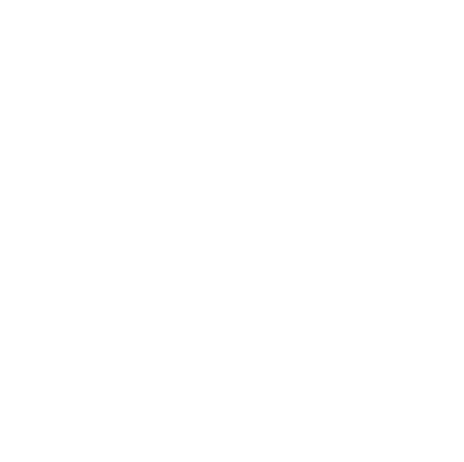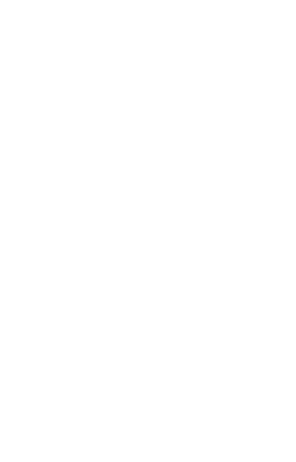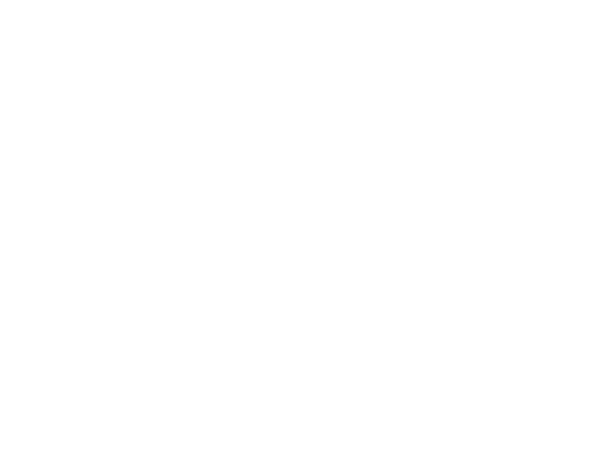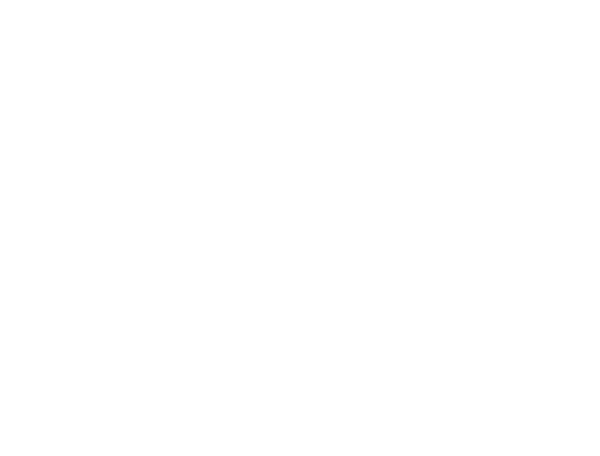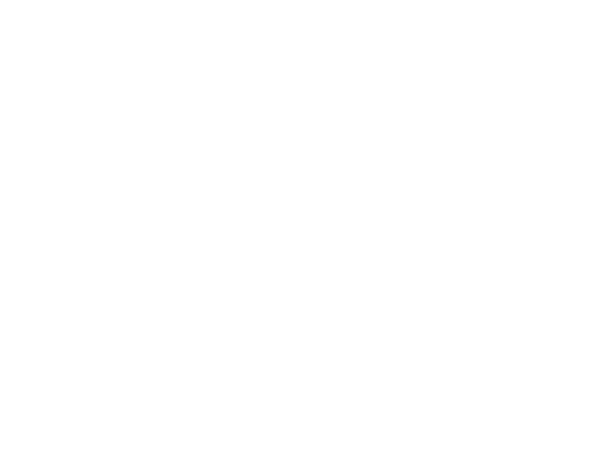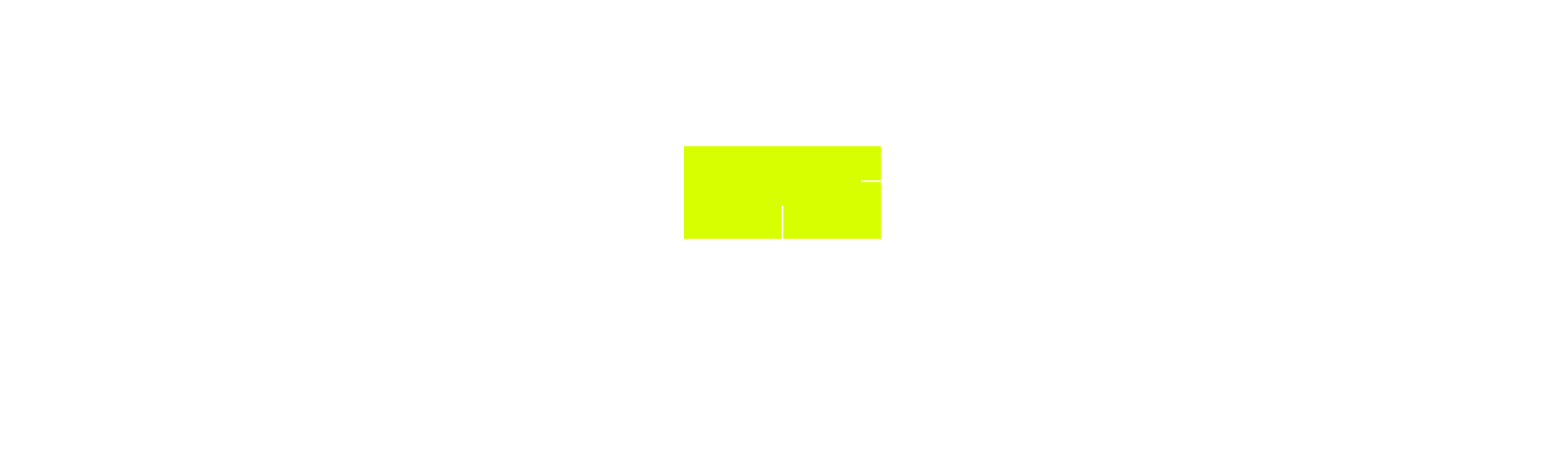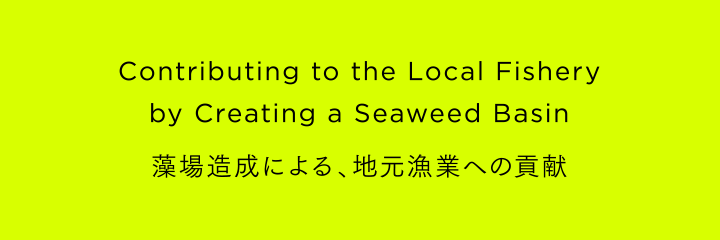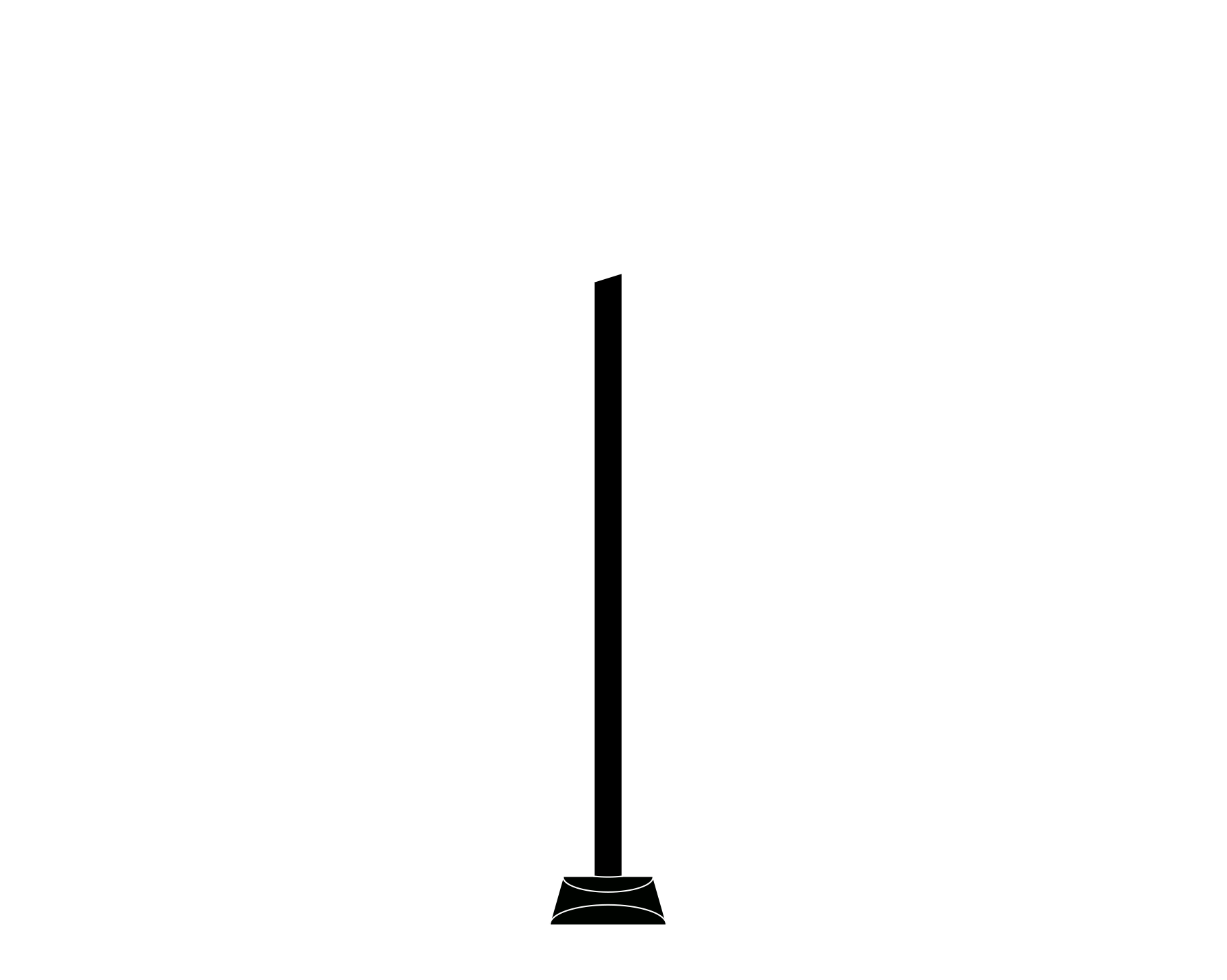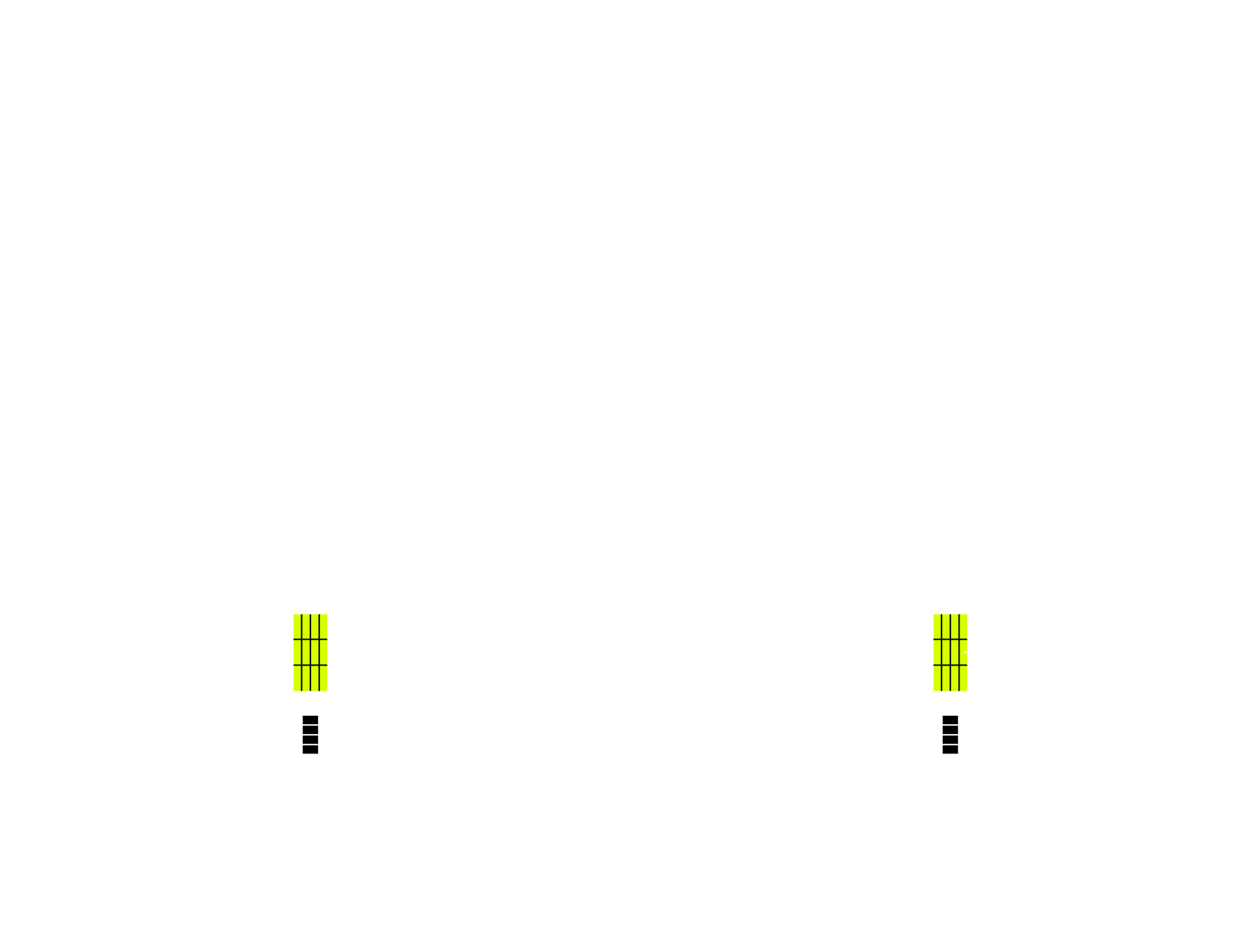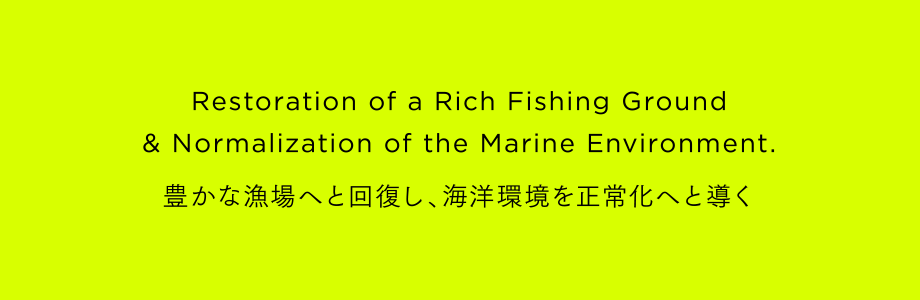今ある海洋環境が、今後も存在し得るために。
環境問題について考えたとき、クリーンエネルギーは選択すべきもの。しかし、開発を伴う事業において、それが環境に与える影響についても、同時に考える必要があります。私たちIFAI(INFLUX FULVIC ACID IRON)は、森林荒廃や海水温上昇など、様々なことが原因で起こる「磯焼け」と、「藻場の減少」に対して、フルボ酸鉄を活用した藻場の造成(回復)を目指す取り組みを行っています。その取組は、洋上風力開発にも活用することで、海洋環境を未来へつないでいく試みでもあります。
MOBA
MOBAは、フルボ酸鉄を活用し、海洋環境を整え、 磯焼けによって失われた漁場を回復させる事業です。
地域の特色を活かした持続可能な漁業を育み、
MOBAの再生事業を通して、地域創生を目指します。
02
The Problem
of Reef-Burning
磯焼けという環境汚染問題
03
About
Fulvic Acid
フルボ酸鉄について
04
Cooperative Research
with Tohoku University
東北大学との共同開発
05
Demonstration Experiment
in Oshima Island
大島での実証実験について
06
Application
to Offshore Wind Power
フルボ酸鉄の洋上風力発電への活用
07
Creation
of New Fishing Grounds
海洋環境の再生
ABOUT MOBA
MOBAについて
MOBA was established to achieve coexistence between the development
of offshore wind power and the conservation of marine ecosystems.
私たち、MOBAは、洋上風力発電における環境への配慮と
保全・地域貢献を目的として設立された事業です。 藻場は魚を、魚は地域をうるおします。
「未来にあるべき海を創る」
日本沿岸の藻場は、1990年代に比べ平均20%も減少しています。
この主な原因は「磯焼け」で、海洋生態系や漁業に多大な影響を与えています。
私たちは、この問題を解決するために有効とされる「フルボ酸鉄」を活用することで、海洋環境の回復を目指しています。
そのことで、藻場や生態系が守られ、海があるべき姿であり続ける未来、それが私たちMOBAが目指す未来です。
THE PROBLEM OF REEF-BURNING
THE PROBLEM OF REEF-BURNING
磯焼けという環境汚染問題
In coastal areas, reef-burning occurs and it is considered as serious environmental problem.
The cause of this problem is thought to be an elution of nutrients,
including iron, due to rising seawater temperature and devastation of the forest.
沿岸地域では、磯焼けが発生し深刻な環境問題となっています。
この問題の原因は、海水温の上昇や森の荒廃により、鉄分を含む養分の溶出量の減少にあると考えられています。
「海の砂漠化」
磯焼けは、「海の砂漠化」とも言われており、海底の岩肌が白くなる現象のことを指します。
この環境汚染問題は様々な問題を引き起こします。
ABOUT FULVIC ACID
フルボ酸鉄について
“Iron fulvic acid” has been attracting attention
as an effective substance against “reef-burning”.
Underwater plankton and algae are substances that
act as a catalyst for absorbing nitrogen, essential for growth.
It is generated over time in the forest and flows into the sea.
「磯焼け」に対し、有効な物質として注目されているのが、「フルボ酸鉄」。
海中のプランクトンや藻が、成長に不可欠な窒素を吸収するための触媒の働きをする物質で、
森林でじっくり時間をかけて生成され、海へと流れてきます。
IRON FULVIC ACID IS MADE IN THE FOREST
フルボ酸鉄は森で作られる
フルボ酸鉄は、地上に落ちた葉や枝が微生物によって分解されるときにできるフルボ酸が、
土の中に含まれる鉄と結合することで生成される物質です。
それが川を介して、海へ流れつき、海中の藻や植物プラクトンの成育に大きく貢献します。
REEF-BURNING BACKGROUND
磯焼けの背景
フルボ酸を含む栄養素が海に供給されないため、
海藻類の成育が阻害されてしまうことで磯焼けを引き起こしていると考えられています。
COOPERATIVE RESEARCH WITH
TOHOKU UNIVERSITY
COOPERATIVE RESEARCH WITH
TOHOKU UNIVERSITY
東北大学との共同研究
We are working on cooperative research with Tohoku University as an approach to
implement seaweed bed restoration projects.
海洋資源の保全のために藻場の改善を行う藻場再生プロジェクトの遂行に向けて、
東北大学と共同研究を行っています。
東北大学大学院農学研究科 水圏植物生態学 青木 優和(あおき まさかず) 教授が
これまで培われた実績と研究力を基盤に、実証実験を進めています。
千葉県沿岸で海洋生物の生育を対象とした実証実験を行い、
全国各地の異なる「藻場」にも応用できる最も効率的で効果的な「藻場再生手法」を開発しています。
青木教授の「水圏植物生態学」では、海洋沿岸域の岩礁生態系において、
海藻に関わる生物間の相互作用システムについての野外調査や実験に基づく生態学的研究を行い、
その成果を海藻養殖や沿岸藻場の保全、再生へ利活用する研究が進められています。
DEMONSTRATION EXPERIMENT
IN OSHIMA ISLAND
DEMONSTRATION EXPERIMENT
IN OSHIMA ISLAND
大島での実証実験
At present, IFAI is conducting a seaweed recovery experiment
using iron fulvic acid in Oshima Island on the Izu Peninsula.
We are continuously verifying the results of seaweed beds created
by iron fulvic acid and recovery of fishing grounds.
現在、IFAIではフルボ酸鉄を利用した藻場回復実証実験を伊豆半島にある「大島」で進行しています。
フルボ酸鉄による藻場造成、漁場回復の成果を継続して検証しています。
PURPOSE OF THE EXPERIMENT
実験の目的
伊豆諸島の海域には、魚類、甲殻類、貝類の生息場所として、岩礁や転石帯などがいたるところに形成されています。
近年、磯焼けや海況変動により、漁獲量の減少が深刻な問題となっています。
IFAIでは、フルボ酸鉄を利用した藻場の回復を継続的に試み、
人工石材や自然石等を使用し、海藻類の着生状況の確認を行っています。
大島は、伊豆半島から、南東方約25kmに位置する島で、
東京からの交通の便も良く、フェリーや飛行機でのアクセスが可能。
地元では、洋上風力発電の計画が持ち上がるなど、実験への理解が進んでいます。
また東京都は、「つくり育てる漁業」への支援に向け、漁港の有効利用などを検討しています。
この仕組みを活用することで、実験後は、アワビの養殖場として開発する可能性があります。
島の南部に位置する、現在休止中の差木地漁港を、実証実験の場に選定。
3年間の占有を認められているこの場所は、行政・漁協などの理解をすでに得られています。
また、近隣には水産試験場があるため、地元の事情に即した指導が受けられます。
ABOUT ARTIFICIAL REEF
人工礁について
藻場造成(海藻着生基盤)のために用いるブロックは、鉄鋼スラグ水和固化体を使用。
この素材は、天然資材の代替として、省エネルギー・省資源に寄与する環境に優しい材料で、グリーン購入法の特定調達品にも認定されています。
鉄鋼スラグには、鉄や珪素など生物必須の元素を含むため、生物付着性に優れ、設置海域の生物改善効果が期待できます。
人工礁ブロック
人工石は天然石に比べ密度が大きいため、潮流や波浪に対する安定性が優れており、
庭生生物や大型藻類の着生基盤として使用。
ABOUT FULVIC ACID UNIT
フルボ酸鉄溶出ユニットの構造と構成材料について
フルボ酸鉄溶出ユニットは、フルボ酸鉄を含んだ溶出材と、人工石で構成。
海況変動に対して安定性を保ちながら、生物付着の基盤としての役割を果たします。
フルボ酸鉄溶出材は、主に、下記の5つの材料で構成。
High-concentration Divalent Iron / Dam Fixed Sediment /
Bamboo Sheath / Shochu Residue / Fish Residue
高濃度二価鉄、ダム固定堆積物、竹皮、焼酎カス、魚カス
ADDRESSING THE LOCAL PROBLEM
地元が抱える問題への取り組み
地元水産業において、近年貝類の漁獲量の減少が問題となっています。
この原因のひとつとされているのが、「アントクメ」という海藻の激減とされています。
「アントクメ」は、大島周辺の浅場では、春から秋にかけて育つ海藻であり、アワビなどの貝類の餌となります。
「藻場造成が、地元の問題を解決する」
アントクメを増殖することが、地元水産業者への最大の貢献だと考え、
増殖漁礁の改良および浮き漁礁の開発を目指しています。
APPLICATION TO OFFSHORE WIND POWER
APPLICATION TO OFFSHORE WIND POWER
フルボ酸鉄の洋上風力への活用
Blocks containing iron fulvic acid and iron ore slag hydrated solidified body
are used in two ways in the construction of offshore wind power generation.
If the water depth is shallow within 5 ~ 10m, it will be installed around the foundation
to play a role in rooting and preventing scouring.
When the water depth is more than 10m, it can be used as a floating fish reef.
フルボ酸鉄や鉄鉱スラグ水和固化体を含んだブロックは、洋上風力発電の建設において2つの方法で活用。
水深が5~10m以内の浅い場合は、基礎周辺に設置し、根固めや洗掘防止の役割を果たします。
10m以上の深い水深の場合は、浮き魚礁として活用することが可能です。
ROCKY REEF TYPE
岩礁性魚礁式施工法
[ 水深5~10m以内の場合 ]
FLOATING FISH REEF TYPE
浮き魚礁式施工法
[ 水深10m以上の場合 ]
CREATION OF NEW FISHING GROUNDS /REGENERATION OF MARINE ENVIRONMENT
CREATION OF NEW FISHING GROUNDS /REGENERATION OF MARINE ENVIRONMENT
海洋環境の再生
By the high concentration of iron fulvic acid contained in the artificial reef block flowing into the sea,
we provide a lot of missing nutrients to living organisms.
人工礁ブロックに含まれた高濃度のフルボ酸鉄が海中に流れ出ることで、不足している栄養塩を生物に多く提供します。
「均衡のとれた生態系の回復」
フルボ酸鉄によって、成育した藻場には、たくさんの魚類や海藻類が育ち、
海藻類と植食動物の関係を整えます。
美しい海を、未来へ。
これまでの研究成果を発展させ、高濃度フルボ酸鉄溶出ユニット(フルボ酸鉄)を基盤技術とした取り組みの成果を、今後社会に提示していくことを検討しています。沿岸海域にこの基盤技術を適用し、不足する栄養塩の補強を行う事により、海藻類と植食動物の関係を整え、海藻群落を大規模に造成し、生物多様性を高め、本来あるべき均衡のとれた岩礁生態系の回復を、より促進していく。「海を正常化する」ことで、未来にも生物が繁栄する美しい海を残していくこと。これが私たちIFAIの使命です。